「生産性ロードマップ戦略」—儲かる工場経営を目指して—第474話 多品種でも儲かるための論点とは?
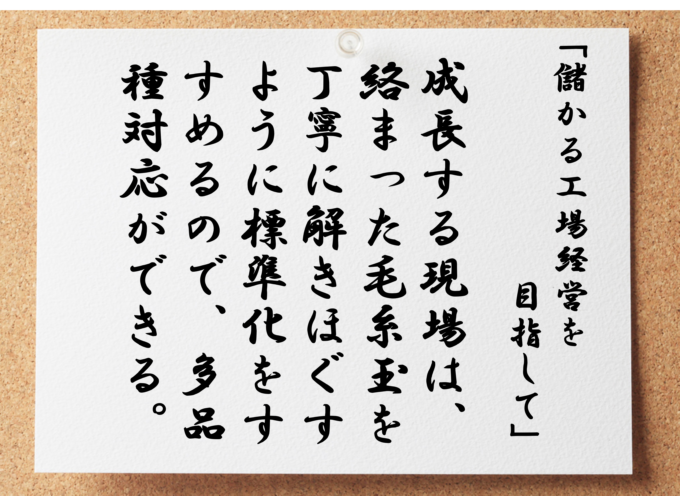
「先生、時間がかかりましたがやって良かったです」
50人規模板金加工メーカープロジェクトメンバーの言葉です。
空調関係の装置や部品をお客様の現場に合わせて製造しています。多品種というよりも、ほぼオーダーメードです。それを少数精鋭の現場でこなさなければなりません。
そこで、経営者は作業指示のベースとなる日程計画の精度を上げたいと考えました。試行錯誤が始まったのです。
そして、メンバーは多品種対応の日程計画、そのためのマスターファイルを地道に作り上げました。時間はかかりましたが、諦めなければゴールにたどり着くのが仕組みづくりです。冒頭の言葉です。
多品種対応であっても、しっかりやりたいことがあります。これは、儲かる製品を造るのに欠かせない論点です。
●儲かる製品とは?
生産形態に次があります。
・規格品生産
・特注品生産
前者はロットや連続生産で「規模の経済」を活かし、後者は個別生産で「一点ものの価値」を活かす事業モデルです。
規格品は製品1個あたりの付加価値額こそ小さいものの、物量で補い付加価値額の規模を積み上げます。経験を積み重ねる中で、現場のスキルも高まりやすくなります。「規模の経済」を活かすので生産コストを下げられるのです。
一方、特注品は、お客様ごとの要望に応えるため1品ごとに高い付加価値を生みます。あなたのために造るので、価格を高められるのです。ただ、造るのに手間暇がかかるので、たくさんできません。
こうした規格品と特注品の特徴を踏まえれば、自ずと、「儲かる製品の姿」が浮かび上がんできます。
・お客様にとっては特注品、製造側にとっては規格品
お客様には自分のために造ってくれたと感じさせる一方で、製造コストを低く抑えられます。しかし実際には「夏と冬を同時に実現するような難題」です。
品種数は儲かる事業モデルを考える論点のひとつになります。
・品種を減らせば、顧客に選ばれる機会を失う
・品種を増やせば、現場が混乱する。
儲かる工場経営を実現するには、「お客様の多品種ニーズに応えつつ、生産コストを規格品並みに下げる」という逆説の両立を追求しなければなりません。品種の多寡バランス決めるのは経営者です。
これはレストラン経営にも似ています。メニューは多彩に見せながら、仕込みは共通化し効率を高める。あるいはスポーツチームが相手に合わせて戦術を変える一方で、基礎練習は同じメニューを徹底してチーム力を高めることに通じます。
ここで問われるのは「付加価値額をどのように積み上げるか」です。単なる売上高の拡大ではなく、固定費回収の発想を変えることが不可欠です。
建築の考え方も参考になるかもしれません。建物を建てるとき、多くの場合、外観はお客様ごとに違っても、基礎工事や構造部分は共通化します。そうすれば、製品の多様性と効率性を両立できるのです。
製造業においても同様に、外からは特注品に見えるが、造る側は規格品的に組み立てる仕組みづくりが儲けにつながります
「お客様の多品種ニーズに応えつつ、生産コストを規格品並みに下げる」を実現させるのが「標準化」です。固定費回収の効率を維持しながら、そこに付加価値を加えます。そして、「標準化」大事な観点が「分類」です。
●標準化の要点は分類にある
デカルトの「方法序説」は「困難を分割せよ」と説きます。多品種でコストを下げる観点も同じです。
・製造プロセスを分割・分解・分類する。
現場でよく使う工程フローは分類の最上位にあり、工程には作業が紐づくという構造になっています。ここで重要なのは「品種ではなくプロセスから分類する」視点です。
・工程→作業の2階層の構造
もし、工程→作業の二段階で処理できなければ、さらに階層を増やすことになります。こうした発想で進めれば、整理が進むのです。
「うちの品種は多いので分類は難しい」という声をよく聞きます。
しかし暗黙知とは、毛糸玉がぐちゃぐちゃに絡まったような状態です。解きほぐすには時間がかかります。しかし、諦めず、やれば必ず一本の糸筋が見えてくるものです。
その糸を地図に描き直せば、迷路が道順に変わり、誰もが同じルートを歩けるようになります。これが標準です。
この現場では、作業をさらに、細分化し、3階層目で90以上の項目に分類しました。その結果、多様な工番に対して、日程計画やリードタイムの算出が可能になり、現場の声も「ようやく見える化できた」と変わったのです。
標準化のための分類は、単なる整理整頓ではありません。分類の段階で得られる数値化の手順は、製造プロセスの構想を明らかにしてくれます。
現場で汗をかいた分、見える化が進むのです。
そして、その構造が、そのままデジタル処理に直結します。チェックボックスやプルダウンといった機能は、裏にある分類体系があるからこそ成り立つのです。つまり標準化とは、デジタル化への橋渡しの役割も担っています。
オーケストラに例えるなら、各楽器の譜面を整理し、パートごとに役割を定義することが標準化。そこに指揮者=デジタルツールが加わって初めて全体が調和します。指揮者役の経営者は「標準化→デジタル化」のシナリオを描けるかどうかも問われるのです。
●標準化は少数精鋭の下支えをしてくれる
多品種対応はお客様からの要望として避けられません。多品種対応は儲かるモノづくりの必須条件と言えます。
しかし、特注品を特注品のままのやり方で造っていては儲からないのです。属人的なプロセスを、誰でも理解できる形に変え、暗黙知を言語化・数値化します。
これが標準化です。腕のいい熟練シェフしか知らない秘伝のレシピを料理本にまとめる作業に似ています。
標準化が進めば多能工化が進み、少数精鋭の現場でも柔軟に対応可能です。計画と実績を比べる生産統制の精度も上がり、管理コストを下げる効果も得られます。
中小製造企業が生き残るためには、価格競争を回避しなければなりません。そのために、多品種であっても、儲けることができる仕組みをつくりたいのです。
さらに、標準化された分類データは、工番ごとのリードタイムの迅速な計算を可能にし、営業担当者が、顧客に納期を即答できる体制を整えます。これは「製販一体」の仕組みづくりにつながるのです。
そして、将来を見据えれば、標準化の延長にあるのは、必然的にDXとなります。それを考えている経営者も多いのではないでしょうか?少数精鋭の現場ならなおさらです。
複雑な工程も、一度標準化されればデジタルツールが自動処理してくれます。チェックボックスやプルダウンといった単純に見える機能も、その背後には緻密な分類と標準化の努力があります。
人材確保が難しい時代に、標準化は少数精鋭を支える「見えない地盤」です。経営者がこの地盤を固めるか否かで、将来の競争力は大きく変わります。
標準化を通じて暗黙知を形式知化し、そこにデジタルを掛け合わせることで、工場全体が“自律的に動く仕組み”に進化します。
これは単なる改善活動ではありません。多品種であっても儲かる工場経営、この事業モデルへの変革の道筋です。
ここまでくれば、経営者は右腕役と現場キーパーソンに工場のことを任せられます。
貴社は儲かる工場経営の姿を描く準備は整っていますか?
次は貴社が挑戦する番です!
成長する現場は、絡まった毛糸玉を丁寧に解きほぐすように標準化をやり多品種対応する
衰退する現場は、絡まった毛糸玉をそのままにして属人的なので多品種対応ができない