「生産性ロードマップ戦略」—儲かる工場経営を目指して—第473話 付加価値額に焦点を当てる理由を知っているか?
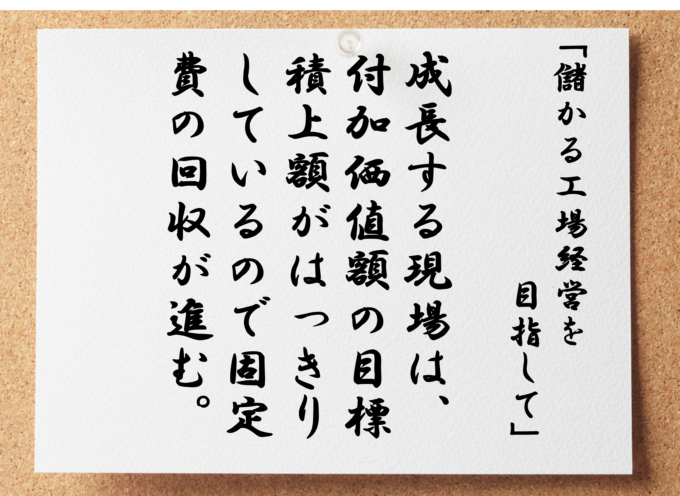
「付加価値額の考え方に慣れていません。」
先日、30人規模の製造設備メーカー経営者から、個別相談をいただきました。論点は人時生産性向上です。付加価値額、いわゆる「儲け」に焦点を当てます。
経営者は、これまで、主に、売上高と利益の多寡で経営状況を判断してきました。多くの経営者と同じであり、これ自体に問題はありません。
ただし、「儲かる工場経営」を目指すには、多角的な視点が必要です。売上だけではなく、「儲け」の観点も求められます。
しかし、その経営者は、付加価値額になじみがありません。冒頭の言葉です。それでも、この数値にこだわって欲しいのです。理由があります。
●売上ではなく付加価値額に焦点を当てる
儲かる工場経営は、利益を真ん中に置いて設計されます。利益は売上高から費用を引いた残りですが、その前提として、「利益が出る構造」がはっきりしていないとなりません。
構造を作るとは、いわば家を建てる基礎工事のようなものです。土台が傾いていれば、立派な柱を立てても意味がありません。
製造業の収益構造においては、付加価値額−固定費の視点が基礎部分です。
固定費は人や設備への投資であり、来期・再来期の収益を支える先行投資と言えます。この固定費は、経営者の意志を持って決められる「動かない石」のような存在です。
一方、付加価値額を、販売戦略によって伸ばせる「流れる川の水」と例えます。
ここで、動かない石でせき止められた川を思い浮かべてください。
川の水量が増せば水位が高くなり、水が、石を超えていけば利益が出るものとします。川の水量が増えて、どっと流れれば、固定費という岩を軽々と越えて、岩の向こう側にある利益の池に水が溜まっていくのです。
売上高は単価や数量、費用など複数の要素が絡み合って変動します。そのため、「売上が上がったから儲かる」とは限りません。原材料費が上がれば、利益は圧迫されます。
そこで登場するのが付加価値額。これは原材料や外注費を除いた“手元に残るお金”であり、利益アップ、給料アップの源泉です。
たとえば、A製品は1個1万円で売れても変動費が8,000円かかるとします。一方、B製品の単価は8,000円ですが、変動費は3,000円しかかかりません。この場合、付加価値額はA製品が2,000円、B製品は5,000円です。
売上高至上主義では、A製品が優秀に見えますが、会社の利益に大きく貢献しているのはB製品となります。見た目の豪華さではなく、“腹持ち”を比べるようなものです。
製品や工番、お客様ごとの付加価値額を比較することで、本当に回収力がある製品が見えてきます。鉄鋳物と電子部品のように性質の異なる事業でも、共通の物差しで比べられるのです。これが付加価値額思考の強みとなります。
●付加価値額の積み上げ方に焦点を当てる
付加価値額を理解したら、次は付加価値額の積み上げ方です。
固定費は、一年間で回収する必要があります。時間は待ってくれません。タイムマネジメントが必要です。
これは、期限の決まった貯金目標に似ています。1年後に100万円必要なら、毎月8万3千円ずつ積み立てなければ間に合いません。経営も同じで、月ごとの積み上げペースが遅れれば、後半に無理を強いられます。
ここで重要なのが「儲かる納期」という考え方です。納期管理をお客様のためだけでなく、自社の利益確保のためにも行います。詰めて、空けて、取り込むのです。
リードタイム短縮では、利益を生む“空き枠”を増やします。現場の段取り改善や工程平準化で作業の詰まりを減らせば、その分、新たな案件を受け入れる余地が生まれるのです。
これは、倉庫の棚を整理して空きを作り、新しい商品を置けるようにするのと同じ発想です。タイムマネジメントによる、工数の整理整頓と言えます。
また、人時生産性は、積み上げ速度を示す重要なメーターです。
たとえば4,500円だった人時生産性を5,000円に引き上げると、同じ時間で稼げる付加価値額が一気に増えます。1日8時間稼働で、社員30人なら、年間数千万円規模の差になるのです。
そして、この指標を、製品や工番、お客様別へ拡張して展開すれば、経営者は多くの有益な情報を手にできます。
製品や工番、お客様別の付加価値額を「規模」に対する「スピード」「手間暇」の関係を把握できるのです。
人時生産性を現場全員と共有し、「あと何日で固定費を回収できるか」を可視化すれば、日々の仕事が、“儲けの積み上げ”という意識に変わります。
さらに、右腕役や現場キーパーソンが、人時生産性向上は利益アップ、給料アップにつながることを実感できれば、現場の動きを確実にかえることができるのです。
経営者は、付加価値額の積み上げ方が大事であることを、右腕役や現場キーパーソンへ指導するのです。経営者の代わりに現場を回してもらうための判断基準となります。
●獲りにいく姿勢に変える
最後に必要なのは「攻め」の経営姿勢です。
固定費を設定し、それを回収する付加価値額を明確にしたら、その数字分の仕事を確保するために動く必要に迫られます。現場が詰めて、空けても、取り込むモノがなければ、儲からないのです。
自ら市場に働き掛け、自ら獲ってこない限り、売上は伸びません。市場は、待っていても、こちらに振り向いてはくれないのです。経営者の仕事場は外にあります。
売上高の結果だけに注目した成り行きの経営から脱却したいのです。
この姿勢は、スポーツでいう“守り一辺倒”と“攻守の切り替え”の違いに似ています。
サッカーで自陣ゴール前に張り付いていても、得点は入りません。ボールを奪ったら前線にパスを送り、ゴールを狙う。経営も同じで、需要のある市場に素早く切り込み、注文を取りに行く動きが必要です。
ある支援先、経営者の話です。その経営者は、これまで紹介や既存顧客からの受注だけでやってきました。そこに付加価値額思考を取り入れたのです。
製販一体の体制を構築し、収益性の高い新市場に営業をかけた結果、1年半の地道な活動が報われ、高付加価値案件比率を2倍にしました。
これは「どこに網を投げるか」を意識的に選んだ成果です。行動する経営者は、必ず、何かを手にできていると、感じています。
冒頭の経営者も「付加価値額の考え方に慣れていません」と言いましたが、慣れるのはこれからで十分です。気づいたその日がスタートライン。成り行きではなく、自らハンドルを握って舵を切りながら、工場経営のステージを高めていきます。
固定費→付加価値額→利益。
この一連の流れを明確に把握するのです。付加価値額を知れば、利益を得るためにやらなければならないことが明確になります。付加価値額は「獲りにいく姿勢」を喚起するのです。
付加価値額を判断材料にできれば、経営者の意識が変わり、現場の動きも変わり、やがて会社全体が利益を生み出しやすい体質に変わります。
次は貴社が挑戦する番です!
成長する現場は、付加価値額の目標積上額がはっきりしているので固定費の回収が進む
衰退する現場は、売上高しかおいかけていないので利益の見通しがたてられない