「生産性ロードマップ戦略」—儲かる工場経営を目指して—第468話 自前だけでやろうとしていないか?
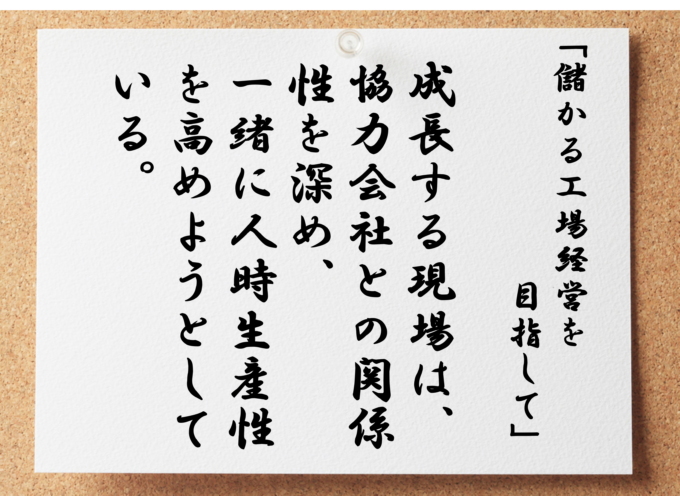
40人規模中小製造経営者と生産能力増の具体策を議論したときのことです。
「工場の一角に、協力会社の現場を設置することも考えられます」
先日、ある40人規模の中小製造業経営者と、生産能力増強の具体策について議論する機会がありました。
いろいろな話の中で、その経営者は冒頭の構想も説明してくれました。
この発言は、限られた経営資源の中で成長しようとする中小製造業の実情と、それを乗り越えようとする強い意志を象徴しています。
この発想は、「生産能力が足りない」という課題に対して、自社設備増強だけではなく、協力会社とも連携して解決しようとするものでした。
その経営者はこう語ります。
「事業を成長させ、売上を拡大したい。そのために新しい顧客を獲得し、生産能力を増やす必要がある。しかし、資金も設備も制約がある。だからこそ、協力会社と一緒にやる方法も考えたい」。
●製造企業は成長しないと生き残れない
内閣府の分析によれば、「付加価値成長率」の増加は、倒産・廃業リスクを大きく低減する傾向があります。存続企業と廃業企業とでは、付加価値成長率に明確な差があり、成長し続けなければ企業は生き残れないことをデータが裏付けています。
儲かる工場経営の要諦は、お客様に選ばれる製品を効率よく造ることにあるので、製造業における成長の鍵のひとつは「工場」です。
何を作るか、どう作るか、ここで企業の将来が決まります。製品は企業の顔であり、工場はその顔を形作る心臓部です。工場が活き活きと稼働していなければ、事業の血流は止まってしまいます。
したがって、儲かる事業モデルでは、「つくるもの」そのものだけでなく、「つくり方」も重要です。お客様に選ばれる製品を、効率よく、そして高品質で製造することが求められます。時代の変化とともに、求められるスピードも品質も高まっています。
その流れに乗り遅れれば、たちまち市場から置き去りにされてしまうのです。
経営者は将来を見据えて、我が社の工場をどのように変えていかなければならないのかを考える必要があります。
製造業における投資先は「設備」と「人材」の二本柱です。この投資は短期間で回収できるものではなく、慎重な判断と継続的な覚悟が求められます。大きな石を転がしながら山道を切り開くようなものです。途中で諦めると、石は元の場所に戻り、山道も切り開かれません。。
工場に投資し続ける企業と、投資を先延ばしにして停滞する企業との差は、数年後、確実に現れます。
今動くか、後で動くか。この決断のスピードも企業の成否を分ける重要な要素です。
●制約ある経営資源を最大に活かす
中小製造企業は少人精鋭です。人材、資金、設備、いずれも限りある中で、最大限のパフォーマンスを引き出すことが経営者の腕の見せ所となります。限られた条件の中でどう結果を出すか、これはまさに知恵比べの世界です。
全てを自社で抱え込むことが、必ずしも最善とは限りません。むしろ、外部資源を上手に活用する「外注戦略」を高いレベルで遂行すれば、効率的かつ安定的に成長することが可能です。
生産能力増強は、設備投資と人材投資がセットで求められますが、先の経営者は、そこに協力会社とのパートナーシップを加えようとしています。限られたリソースを最大限に活用し、自社の競争力を高める上で非常に有効な考え方です。
外注には「儲けが外に流れる」というイメージがありますが、事業モデルによっては、逆に利益を生み出す成長エンジンになり得ます。特に、コア技術に集中し、その他を協力会社に任せる戦略は、柔軟で安定した経営につながります。
自社の強みを最大限に活かし、周囲と連携することで弱みを補う。
バランス感覚が重要です。
重要なのは、協力会社を「単なる外注先」としてではなく、「事業成長のパートナー」と位置付けることです。その視点に立てば、固定費の変動費化というコスト削減だけではなく、共に利益を生む共同体の形成に変わります。
外注戦略を共闘戦略、成長戦力に進化させることができれば、双方にとって持続的な成長の土台となります。
さらに、外注先との協力関係を築くには、単なる発注者としての立場ではなく、「お互いの成功を願う仲間」としての姿勢が求められます。この心構えが、信頼を育み、強固なパートナーシップを生むのです。
●協力会社との信頼関係を深める
協力会社を自社工場の一角に迎え入れるやり方は、まさにこの外注戦略を、極限まで高めたものです。協力会社と文字通り「共に働く」ことで、一体感とスピード感を飛躍的に高められます。
同じ空間で、同じ時間を共有し、同じゴールを目指す。
この関係性は、単なる契約を超えた「現場レベルの連携」を生み出します。
現場で隣り合って働くけば、現場の声がダイレクトに届き、改善のスピードも格段に上がるのです。小さなトラブルも即座に共有でき、互いに助け合う文化も自然と根付きます。
ただし、この戦略は諸刃の剣です。
もし受注量が大きく減少すれば、協力会社は負の影響をもろに被ることになりかねません。協力会社の設備や人員を頼りにするということは、それだけ、マイナスの負担も協力会社にお願いすることにもなるからです。リスクヘッジが必要かもしれません。
・一定量の受注を確保する営業戦略の徹底
・協力会社とのリスク共有に関する契約の整備
・柔軟にスペースを活用できる工場レイアウトの設計
・市場の変動に合わせた生産調整ルールの策定
・複数の協力会社と連携し、供給リスクを分散する仕組み作り
などなど
これらは一例に過ぎませんが、こうしたリスクヘッジをしながら、協力会社と共に成長を目指す姿勢が、豊かに成長したい中小製造業に求められるのです。
経営資源には制約があるからこそ、工夫も欠かせまん。
協力会社と一緒に成長する。その覚悟があれば、大きな利益と安定した将来を掴む可能性は大いに広がります。
重要なのは、協力会社の視点に立ち、双方が安心して共に歩める環境を築くことです。自前にこだわる必要はありません。
●右腕役と現場キーパーソンへの指導をやっているか?
経営者は市場の変化を先読みし、外に出て顧客を掴みに行かなければなりません。その間、工場は経営者がいなくても安定して回り続ける必要があります。これが実現できなければ、成長のための社長業に専念できません。
そのためには、現場を任せられる右腕役と現場キーパーソンの育成が不可欠です。もし右腕役とキーパーソンが育っていなければ、経営者は安心して外に出ることができず、事業の拡大は夢のまた夢です。
右腕役とは、単に現場の責任者ではなく、経営者の思いを深く理解し、経営判断の一部を肩代わりできる存在です。現場キーパーソンとは、現場で実務を動かす実力者であり、現場に根差した仕組みをしっかり回せる人材です。
こうした人材が機能していれば、経営者は安心して社外活動に集中できます。
弊社では、右腕役と現場キーパーソンが工場を自主的に動かし、経営者が本来の社長業に集中できる体制づくりを重視しています。協力会社との高度な外注戦略を実践するにも、この社内体制がしっかり整っていることが前提条件です。
右腕役と現場キーパーソンを育成し、協力会社との信頼関係を築き、柔軟で強い外注戦略を進める。こうした仕組みがあれば、中小製造業は持続的に成長し続けることができます。
成長したい、でも自社のリソースには限界がある。そんな葛藤を抱える経営者こそ、こうした外注戦略が大事になりませんか?
次は貴社が挑戦する番です。
成長する現場は、協力会社との関係性を深め一緒に人時生産性を高めようとしている
衰退する現場は、全て自前でやろうとするが経営資源に制約があるのでやり切れていない