「生産性ロードマップ戦略」—儲かる工場経営を目指して—第385話 自主性を引き出す動機付けに必要なことは?
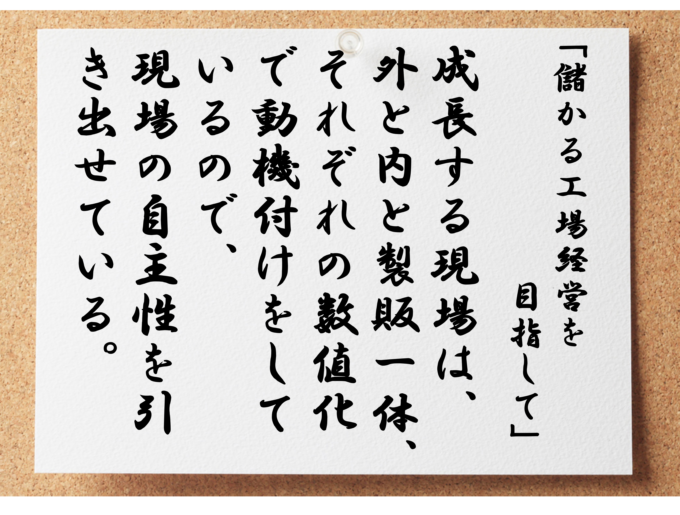
「売上高計画値で現場へ指示を出すようになりました。」
半年ほど前から人時生産向上PJに取り組んでいる素材メーカー経営者の言葉です。
能力VS負荷。
お客様から仕事の問い合わせに対して受注可否判断をします。経営者の見立てでは能力>負荷にも関わらず、現場からは能力<負荷との声が上がり、失注することが度々起きています。
当然ですが、売上高が横ばいです。
PJに着手するに当たって、目標を設定しました。計画値です。儲かる工場経営3つのフィールドでの数値化をやりました。その中のひとつに売上高の計画値があります。
先月、ある案件の受注可否判断をしていたときのことです。
従来なら、忙しくてできないとの判断に至る場面で、右腕役の担う幹部が、これまでとは違う指示を現場へ出しました。
冒頭の言葉です。
経営者の仕掛けが功を奏してきました。経営者の意志や意図が以前より浸透しています。
現場も、ウチの事情ではなく、お客様の事情、経営者の意志や意図を判断基準にして考えるようになってきたようです。
中小製造企業は、計画値を持たないと受動的な事業活動に留まってしまいます。
先の企業がそうでした。先の企業は年商の30~40%を占める主要なお客様と長年、お付き合いをしてきました。先代が開拓したお客様です。
お客様の現場へ製造設備を納入してきました。先代が築き上げた信頼関係が土台にあります。こうした環境では、積極的な販売活動をやらなくても一定規模の安定受注が可能です。
経営上の目標値を設定しなくても、事業を継続させられました。
しかし、現経営者の時代になり、お客様の事業環境も変化します。先代との繋がりを知っている人も減り、加えて市場動向が見通せなくなってきたことによる影響が出てきたのです。
主要なお客様からの受注量が2年前から減少傾向にあり、そのまま今日を迎えています。
これまで、受動的な事業活動に留まっていた先の企業では、売上高を結果としてしか見ていませんでした。売上高が減少するのはしかたがないと考えるだけです。
その思考は現場にも伝播します。受注量が減少すれば、それに伴ってこなす仕事量が減るわけですが、現場も、その仕事量に「合わせて」仕事のペースを決めるだけです。
現場は手待ちで暇な状況にしたくはありません。納期に合わせたぼちぼちペースで仕事をつなぎます。その結果、リードタイムが間延びするのです。この環境を放置しておくと、受注量が少々上振れしただけで、「忙しい」「間に合わない」との声が出てきます。
チーム力は筋力と同じです。間延びしたやり方を是としていると、それにあったやり方に落ち着いてしまいます。
受注減の時、誰一人として、外から仕事を獲ってこようと考える人がいなかったのです。そんな思考回路の現場になっていました。動機付けが必要です。
付け付けがないと、チーム力MAXは維持できません。
そんな現場をいくつも目にしてきました。
先代から引き継いだ事業が上手いっているうちは、計画値を持たない受動的な事業活動でも構いません。上手くいっているのですから。
ただし、問題は安定受注ができなくなったときです。
チーム一丸となって巻き返しを図れるかどうか?
計画値VS実績値の視点を持っていれば、受注の減少傾向に気付くのです。
例えば、移動累計です。
売上高の実績が計画対比で不足していたらどうするか?
獲りに行くしかありません。全社一丸、製販一体。外での活動を活発化させるのです。ここから能動的な事業活動が始まります。
下請け型モデルが多い中小製造企業が、自社で生殺与奪の権を少しでも握りたかったら、従業員の協力を得て、経営者が市場に働きかけるしかないのです。
売上高の機会は外にしかありません。内にはないのです。
ただし、工場で仕事をする内のメンバーにも使命があります。
受注が決まったら、それをいつでもこなせるように、刀を一層、研いで切れ味抜群にしておくことです。リードタイム短縮の高みを目指します。
合理化フロンティア、2つの設計、見える化等々。LT短縮手法はスキルです。訓練すれば高められます。終わりはありません。
そして、こうしたことは余力のあるときにしかできないのです。
もし、手が余る内のメンバーがいたら、外の支援をします。獲りに行く活動はいくらやっても、「もう十分だ」はないからです。
製販一体現場は受注量の多寡に関係なく、いつでも必要な課題を設定して、積極的に動いています。右腕役がその活動を主導しています。
そして、現場の自主性を引き出すには動機付けが不可欠です。
目標の設定が動機付けになります。計画値です。
計画値があれば、実績値と比べられます。比較すれば差異を認識できるのです。差異の認識が動機付けとなり、自主性が引き出されます。考える=比べるです。
目標を数値で示す効果はここにあります。
マネージャーたるものは、上は社長から下は職長や事務主任にいたるまで、明確な目標を必要とする。(出典:マネジメント「エッセンシャル版」)
ドラッガーの言葉です。
成果は計測できなければならないので、多くの目標は数値化されます。儲かる工場経営のフィールドは3つです。外と内と製販一体。それぞれのフィールドにおける数値化が必要です。
・外では売上高、新規お客様開拓数、既存お客様訪問数、展示会参加数等。
・内では納期遵守、リードタイム、時間当たり出来高、提案改善案件数等。
・外と内をつなぐ製販一体では利益、見積もり、付加価値額(粗利)、人時生産性等。
製販一体の目標で外と内をつなぎます。特に人時生産性が大事です。利益アップ、給料アップは人時生産性を高めない限り実現できないからです。
外は外だけ、内は内だけの目標では、チームが全社一丸、製販一体にはなれません。3つのフィールドでの目標が必要です。外と内をつないでチーム力を発揮します。
人時生産性は、従業員が人生を掛けて手にしようとしている成果を計測するのに欠かせないものです。現場の自主性を引き出す動機付けはココにあります。
外と内をつなぐ数値でなければそうなりません。
分母の場合分けもカギです。
先の経営者は現場の自主性を引き出す動機付けの一歩目を踏み出しました。受動的な事業活動から能動的な事業活動へ変えていくためです。
外に焦点を当てた売上高の計画値からです。足りなければ獲りに行く思考回路を右腕役と現場キーパーソンに持たせます。
進捗確認、フォローと評価も大事になるのは言うまでもありません。
次は貴社の番です!
成長する現場は、外と内と製販一体、それぞれの数値化で現場の自主性を引き出している。
成長する現場は、計画値がないので成り行き経営になり納期遵守さえやればいいと考える。