「生産性ロードマップ戦略」—儲かる工場経営を目指して—第458話 戦術的リードタイムでお茶を濁していないか?
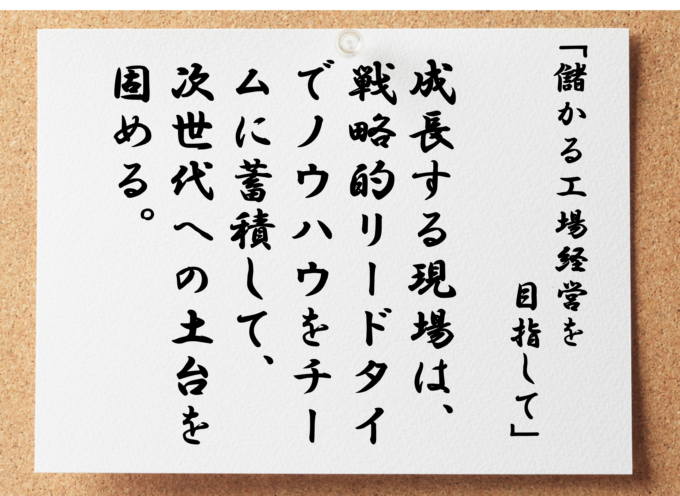
「受注量が増えるとまた混乱するかもしれません」
これは、先日の定例フォロー会議における、組立系メーカー工場長の言葉です。
プロジェクトも3年目。PJメンバーは、時間をかけて構築した工程管理の仕組みを実践モードで回し始めました。工場長は仕組みの効果を体感しています。
例えば、納期をお客様へ即答できるようになりました。作業指示の精度も上がっています。そうなると、フォローと評価ができるのです。
また、遅れの認識が、納期直前から、日々の段階で、できるようになりました。判断基準があるからです。そして、その分、工場長には余裕が生まれています。
付加価値額の積み上げや生産性でも、良い兆候が見られるのは喜ばしい状況です。ただ、受注量は横ばいが続いているので、構築した仕組みが、収益的に大きく貢献する段階には至っていません。
これからトップを先頭に、製販一体で外へ攻勢をかけます。
受注量を積み上げ、工場は、受注した案件をドンドンさばくのです。忙しいからできないという対応はもうしません。そのための仕組みがあります。あとは実践を通じて、仕組みを修正、強化するだけです。
ただ、工場長からは冒頭の言葉が出てきました。
受注量が増えれば、現場は混乱するかもしれません。従来、何度も経験してきたことです。しかし、従来のように混乱し、すったもんだが起きても、今度は、従来と違います。そのことを工場長へ伝えました。
●戦術的リードタイムと戦略的リードタイム
工程管理ができているところと、できていないところの違いは、「遅れ認識のやり方」に表れます。
・納期直前で遅れを認識する
・日々の工程進捗で遅れを認識する
工程管理ができていないと、結果として前者になります。工程フロー分類と標準リードタイムの体系がないからです。これらがなければ、的確な中日程、小日程ができません。だから、納期設定でサバを読むことになります。
誰でも、わざわざ、危険を冒しません。工程管理の仕組みがないと、経営者の知らないところで儲かりにくい土壌になっていくのです。加えて、そのサバを読んだ納期にも関わらず、納期直前で混乱が起きます。的確な中日程、小日程がないからです。
現場の時間軸上には、着手と完了という時刻が存在します。指示導線「指示する人」がこれら2つを小日程で管理するのです。
そして、作業指示の精度を裏付けるのが中日程です。1日単位、半日単位、2時間単位の精度。指示の時間精度は高ければイイというものではありません。指示導線次第です。的確な精度を見極める必要があります。
したがって、的確な中日程、小日程がなければ、サバを読んだ納期でも、結局、遅れ認識が納期直前になるのです。こうなると、納期直前で「緊急すったもんだ対応」です。
残業、休出、製造順番突発入れ替えなど、無理やりリードタイムを短縮し、納期になんとか間に合わせます。先の工場長のこれまでの仕事ぶりはこんな感じでした。
都度、身体を張って乗り越えます。乗り越えたら、やれやれ、終わった、お疲れさま!で仕事がクローズです。
このリードタイムは、「戦術的リードタイム」です。長期展望はありません。乗り越えれば終わりです。局地戦には勝利しますが、戦局全体を見たとき、それがイイのかどうかは、別の話となります。
中小製造経営者は、日々の工程進捗で、遅れ認識するやり方を指導しなければなりません。戦術的リードタイムのやり方だけでは、少数精鋭の現場が疲弊するからです。
次世代へ向けて、若手が「残業、休出、製造順番突発入れ替えなどのやり方」を喜んでするとは思えません。やり方を変える必要があるのです。
工程フロー分類と標準リードタイムの体系を準備することになります。標準を作成し、仕組み化を進めるのです。その判断基準は標準リードタイムです。これがあればbeforeとafterを設定できます。
現状対比で生産性を20%高めたかったら、リードダイムをそれに合わせて短く設定してすればいいだけです。後は、それを実現させるよう、各工程に挑戦を促します。こうして設定されたリードタイムは、「戦略的リードタイム」です。長期的展望に立っています。
司令官は局地戦の勝利だけで満足していてはいけません。戦局全体を見渡し、競合先に勝てるよう、時間も味方に付けて、戦略的な選択をするのです。
日々の工程進捗で遅れ認識しながら、製販一体で戦略的リードタイムに取り組みます。仕組みがあれば、型が明確です。型があれば、次世代を担う若手も頑張れます。
●モグラ叩き型と蓄積型
戦術的リードタイムで、都度、乗り越えるやり方を続けていても、チームにノウハウは蓄積されません。属人的に経験が積み上げられるだけです。
「残業、休出、製造順番突発入れ替えなどのやり方」の蓄積が、無意味とは言いません。ただ、属人的になりがちです。先の企業では工場長です。
協力してくれそうな従業員にお願いし、それでも足りなければ、工場長自身が身体を張ります。乗り切ることが目的です。都度、モグラ叩きで対処します。
これは、これで、足元の収益確保には大事です。こうした緊急対応を主導する職制がいることに、ひとまず安心はできます。
ただし、そのまま、5年後、10年後の次世代になったらどうなるか?
モグラ叩き型では、ノウハウがチームに蓄積されません。
そして、戦術的リードタイムしか持たない状況で、受注量が増えるとどうなるか?
従来の繰り返しです。モグラ叩き型では、現場は辛いままです。
仕事のやり方を蓄積型に変えなければなりません。そこで、戦略的リードタイムです。各工程に挑戦を促せば、ノウハウがチームに蓄積されます。
工程管理の仕組みづくりでは、
・受注票からリードタイムデータを得る流れ
・さらに、そこから作業指示を出す流れ
・最終的に、遅れを認識して手を打つこととマスターファイルを検証する流れ
受注票受付からマスターファイル検証までの流れを構築します。
こうした仕組みがあっても、受注量が増えれば、現場に混乱が起きるかもしれません。しかし、このすったもんだは、従来のモグラ叩き型の時とは違います。混乱の中で、チームにノウハウが蓄積されます。
仕組みと言う「型」があるからです。情報を、的確に、早く流すことが、仕組みの目的となります。混乱やすったもんだ仕組みを強化する機会です。
そうして「型」がブラシュアップされます。こうやってチームにノウハウが蓄積されるのです。仕組みができればそれからが本番です。混乱を機会に、仕組みは改善され強化されます。
仕組みがあれば、混乱を機会に、ノウハウが蓄積されるのです。しかし、仕組みがなければ、ただの混乱に終わります。
蓄積に繋げられるよう、現場へ仕組みづくりを指導して欲しいのです
先の工場長に上記を説明しました。
「先生、なるほどそうかもしれません」とは先の工場長の言葉です。今は、周りから助けをもらえる状況になっていることを知り、前よりは、上手くできそうな気がしてきました。ノウハウはヒトではなく、チームに蓄積させます。そうでないと、次世代の若手が辛くなります。
貴社は戦術的リードタイムでお茶を濁していませんか?
次世代に向けたやり方に変えましたか?
成長する現場は、戦略的リードタイでノウハウをチームに蓄積して次世代への土台を固める
衰退する現場は、戦術的リードタイムで属人的な仕事のやり方のまま、次世代が辛くなる