「生産性ロードマップ戦略」—儲かる工場経営を目指して—第477話 若手は「教えてください」と手をあげているか?
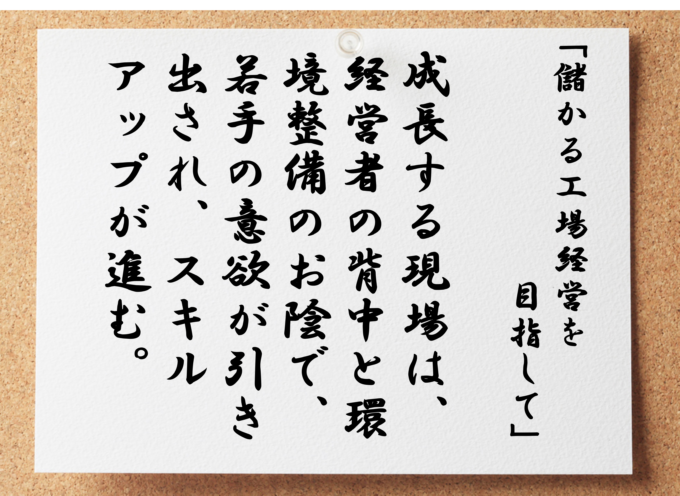
「自分でやろうとしなくなります。」
セミナーに参加いただいた経営者の言葉です。
現場スキル水準の底上げは、中小製造企業での生き残りに欠かせません。少数精鋭で、人材確保が厳しい中小製造現場では、今いる従業員が頼りの人材です。
若手には、短時間で一人前になってもらいたいと、経営者なら誰でも考えます。若手には意欲を持って学んでもらいたいのです。
座学や外部で学ぶoff-JTもありますが、やはり学びの中心はon-JTになります。そうであるなら、若手人材が、なにか分からないことがあったら、「教えてください。」と言える環境が大事です。
先日の弊社主催セミナーの中で、人材育成について、現場で直面している問題点を語ってくれた経営者がいます。冒頭の言葉です。
分からないことがあるたびに、教えていると、自分で考えなくなるのが、その経営者の困り事でした。若手が、自ら学ぼうとしないと感じています。
ただ、問題の本質は違うところにありそうです。その本質とは?
●学びの中心はon-JTがいい
人材育成における学びの中心は「on-JT(実務を通じた学習)」であることが重要です。
学びの分配「70-20-10モデル」があります。これは、「実務から学ぶ」、「人から学ぶ」、「座学で学ぶ」の比率は70:20:10が望ましいとする経験則です。
米国の人材開発研究所 Center for Creative Leadership(CCL)が1996年に書籍で発表しました。中間管理職・リーダー職を中心とした企業人材750人を対象に、「最も学びが大きかった経験は何か」を調査し、キャリア成功者の学習の源泉を数値化しました。
その結果、次のようでした。
70%:業務そのもの(実践経験)から学んだ
20%:上司・先輩・同僚からのコーチング・フィードバックで学んだ
10%:研修や講義などの座学から学んだ
人から教わり、その場で実践する。この経験を重ねるやり方が、コスパが良さそうです。分からないことは、さっさと人から教わります。そして、業務を実際にこなし、失敗と成功を重ねることで、知識が「自分の血肉」になるのです。
いわゆる「on-JT(実務を通じた学習)」です。
このon-JTは「ただ現場で作業すればいい」というわけではありません。正しいやり方を最初に身につけることが不可欠です。
我が社には我が社のやり方があります。だからこそ、実践の前にきちんとした指導が必要なのです。正しい土台なくして成果は積み上がらない──これは家づくりと同じです。
教わる→実践→フィードバック→再実践──このサイクルを回すことで、若手従業員は短期間で成長します。
逆に、このステップが抜けると、勝手な方法を身につけ、結果として間違ったやり方を覚えてしまうリスクがあるのです。
ここで重要なのは、現場教育はコストではなく投資という視点です。指導に時間をかけることは、企業の競争力を生む「見えない資産」になります。
「人から教わり、その場で実践する」──この繰り返しこそ、最もコストパフォーマンスの高い学び方です。中小製造業の人材育成においては、育成のスピードと精度が企業存続を左右するといっても過言ではありません。
貴社の現場では、若手が学び続けるサイクルは機能していますか?
●「教えて下さい」の環境づくりをした結果どうなっているか?
次に大切なのは、「教えてください」と言える環境を整えることです。
若手従業員が疑問を抱いたとき、気兼ねなく質問できるかどうかで、育成スピードは大きく変わります。知りたい欲求があるときに教えてあげるのが最も効果的です。
例えば、新入社員のAさん。入社したばかりです。右も左もわからない状況でしたが、社長からこう言われました。
「分からないことがあったら遠慮せず、どんどん先輩に聞きなさい。それがうちのやり方だから。」
実際に、先輩たちが快く教えてくれる環境です。忙しい場面であっても、周囲の人たちは、丁寧に教えてくれます。
Aさんは、質問するたびに知識を吸収し、即実践しては改善を繰り返しました。気づけば短期間で仕事を任せられる存在に成長していたのです。
できることが増えれば、面白くなります。先輩方や周囲の人たちも「もう、1人でできるようになったのか、早いね~」と褒めてくれるのです。
仕事で一人前と認知されると、嬉しくなります。他人から評価されることに勝る喜びはありません。こうやって、今年入社した若手従業員は短期間で自立していきました。
ここで重要なのは、若手の意欲は「教える側の姿勢」で大きく変わるということです。
先輩や周囲が「あなたを育てたい」と思っている環境では、若手は自然と前向きになります。逆に、質問しづらい雰囲気では、学びが止まり、結果的に人材が定着しません。
つまり、質問できる環境は人材定着率アップにも直結するのです。
一方で、人に教わると自分でやろうとしなくなる若手、そもそも質問すらしない若手もいます。人材育成は「絡まった毛糸玉」のように、一筋縄ではいきません。
だからこそ、成功している現場に共通する要素──「先輩や周囲が丁寧に教える文化」「成長を見守る心遣い」──を意識することが、解決の糸口となります。
仕事の忙しさを理由に、教えてくれる雰囲気を醸成できない現場で、若手人材がどんな行動をとるかは明らかです。
貴社では、若手が安心して「教えてください」と言える雰囲気が整っていますか?もし整っていないなら、環境づくりの見直しから始める必要があります。
●結局、経営者の背中を見ていると考えずにはいられない
弊社の支援先の中でも、若手育成に成功している現場には必ず共通点があります。それは、経営者自身の「背中」です。
経営者がどれだけ真剣に未来を描き、言葉と行動でそれを現場に示しているか──この姿勢が若手従業員の意欲を決定づけています。
会社のビジョンは、言葉ではなく「経営者の熱量」で伝わります。社長が必死に外に飛び出し、新しい仕事を取ってくる姿勢は、まるで工場を照らす灯台の光のようです。
その光があるからこそ、若手は迷わず進むことができる。逆に、灯台が暗ければ、どれだけ声をかけても若手は不安で立ち止まってしまいます。
度々、申し上げていますが、現場は経営者の鏡です。
また、経営者の姿勢は、トップダウンとして、経営者層から現場へ、水のように流れていきます。上流の社長が澄んだ水を流せば、下流の現場は自然と豊かになりますが、濁った水を流してしまうと、下流はよどむのです。
つまり、現場の「学ぶ雰囲気」は、社長自身の言動から生まれます。
ここで強調したいのは、「熱意は伝染する」という事実です。経営者が挑戦していれば、社員も挑戦しようとし、結果として組織全体の文化が変わります。
若手人材には、そもそも、「分からないことを知りたい!」という欲求を抱いてもらわなけれならないのです。それは、経営者の背中次第と考えずにはいられないのです。
実際、現場でお互いに教え合い、挑戦を楽しむ空気を持つ会社ほど、社長のメッセージと行動に一貫性があります。
小手先のマニュアルや指示ではなく、経営者の情熱そのものが、若手の意欲に火をつける燃料になっているのです。さらに、経営者が「失敗を恐れずに挑戦する姿」を見せると、若手も安心して挑戦できるようになります。
結局、若手従業員は経営者の背中を見て育ちます。御社の現場ではどうでしょうか。
もし「うちの若手は教えてもらうことに熱心ではない」と感じるなら、まずは経営者自身の背中と、環境整備の有無を確認する必要があります。
ただし、経営者自身では気付かないことも多いので、少々、厄介な問題です。
この点には留意が必要です。
次は貴社が挑戦する番です!
成長する現場は、経営者の背中と環境整備のお陰で若手の意欲が引き出され学びが進む
衰退する現場は、仕事の忙しさを理由に教えてくれる雰囲気に欠けるので若手は伸びない