「生産性ロードマップ戦略」—儲かる工場経営を目指して—第481話 経営者の意志を製販一体の場で伝えているか?
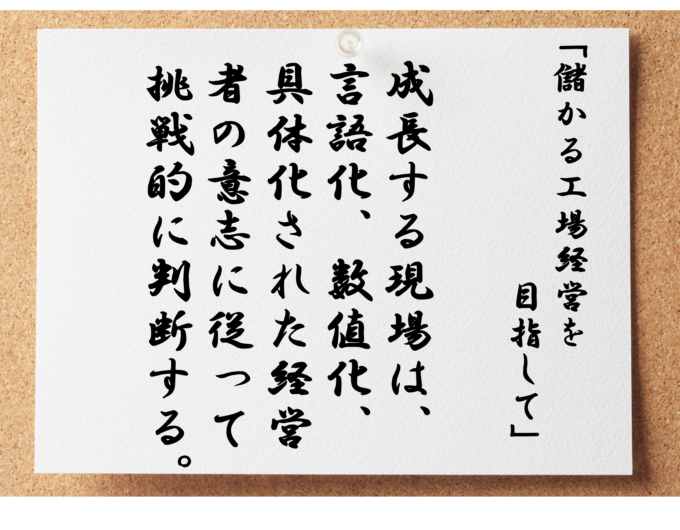
「新規受注検討リストが重要な役割を果たします。」
プロジェクトが2年に入った切削加工メーカー経営者の言葉です。
日程計画の仕組みづくりを終え、現場管理体制をほぼ完成させました。ただ、受注が獲得できていません。現在、課題の対象領域は、「内」から「外」へ移行しつつあります。
内がどんなに強化されても、受注がなければどうしようもないのです。受注確保が次の課題です。10年前からの経緯が影響しています。
課題解決のキーワードは「製販一体」です。新たな受注を製販一体で獲りに行きます。そこで大事な役割を果たすリストがあるのです。
経営者はこれが必要であると以前から考えていましたが、やっと実践する時が来ました。冒頭の言葉です。
●負のスパイラルに陥った経営者
かつては年商5~6億円を誇った会社も、今や4億円規模へと縮小しています。背景には「負のスパイラル」があります。ベテラン社員が残業や休日出勤も厭わず案件を抱え込み、どんな無理難題も力技でこなしていた時代は過去のものとなりました。
頼みの綱だった中堅・ベテランは定年や退職で去り、人員は減少しました。穴埋めにアルバイトやパートを入れても、ものづくりの底力はどうしても低下します。
まるで城を守る兵士が減り、城壁の穴を臨時の板でふさいでいるような状態です。風雨に耐えられず、次第に内部が侵食されていきます。納期遅れが増え、顧客の信頼は揺らぎ、失注が積み重なります。
営業もかつてのように「少々の無理をしてでも守る」という姿勢を取れなくなり、確実に守れる案件だけを受けるようになります。
その結果、顧客の要望に応えられず、さらに信頼を失う――この悪循環は、渦を巻く流砂のように会社を飲み込んでいきます。
経営者が「営業はもっと積極的に動け」と指示しても、営業担当者の胸中には過去の失敗の痛みが残っています。納期トラブルで顧客から叱責を受けた経験が、彼らを臆病にしているのです。
顧客の要求は、川の流れのように途切れなく続きますが、その水流を受け止める勇気を失った営業は、安全な小さな水たまりだけを選んで汲みとっています。10年前の積極的な雰囲気は、残念ながら、知らず知らずのうちに、雲散霧消したのです。
こうして「納期遵守ができない→信頼を失う→案件を断る→信頼をさらに失う」という負のループが、知らず知らずのうちに形づくられていきます。「知らず、知らず」は怖いです。
これは製造と販売が互いに相手のことを理解する機会がなく、ずるずる時間だけが経過した結果でもあります。
守りに入った製造は「これ以上迷惑をかけられない」と、余裕のある納期を設定するのです。一方、営業も「工場は無理を聞いてくれない」と尻込みをします。
これでは、駆動輪である営業部門のパワーが出ないのです。スピードが出ません。製造もパワーのない車体をコントロールできず、モタモタします。そうしているうちに、競合他社に追い抜かれているのです。「知らず、知らず」のうちに。
経営者が痛感したのは、この負スパイラルから抜け出すには、もはや「営業の頑張り」や「製造の努力」だけでは足りないということです。チームになっていません。
つまり、受注が取れないのは「人がいないから」でも「工場が弱ったから」でもなく、販売と製造が一つの方向を向いていないからです。
この認識に立ったとき、負のスパイラルを断ち切るには、製販一体の連携しかないとの考えに至ります。そして、経営者は、以前から考えていた道具の導入を実践するのです。
●製販一体がなぜ必要なのか?
製造業の事業構造は、2輪の前輪と後輪のように、駆動力を生み出す「販売」とその駆動力をコントロールする「製造」の二つの連動で成り立っています。
駆動だけ、コントロールだけ、片方だけでは2輪は上手く前進しないのです。販売は市場で戦い、製造は工場で生産する――役割は違いますが、どちらも欠かせません。
市場では顧客が決定権を握ります。顧客の要望に応えられなければ、どんなに工場が効率的でも見捨てられます。一方で、工場の事情を無視した過剰な約束をすれば、すぐに現場は破綻します。だからこそ、両者の歩調合わせが不可欠なのです。
しかし、実際には、販売と製造は異なる言語を話します。営業は「売上」と「顧客」で語り、製造は「生産能力」と「納期遵守」で語ります。
製販一体の本質は、互いの事情を「翻訳」して共有することにあるのです。共通用語を持てば、駆動力を生み出す「販売」とその駆動力をコントロールする「製造」が連動します。
営業は工場の余力や能力を理解し、製造は顧客の声や市場の動きを知る。その橋渡しをしなければ、双方は守りに入り、せっかくの改善努力も試せません。
実際、このメーカーでも、1年間のプロジェクトによって工場の納期対応力は上がっていましたが、営業はそれを活かしきれていませんでした。
そこで必要になるのが「新規受注検討リスト」です。これは単なるリストではなく、経営者の意志を形にした羅針盤です。
従来は営業担当者の頭の中にしかなかった情報を見える化し、製造と営業が同じ時間軸で議論できるようになります。
これにより「どの案件に挑戦すべきか」が客観的に判断でき、経営者は判断の責任を負う体制ができるのです。属人的な責任追及から解放され、挑戦の姿勢を取り戻せます。
製販一体は単なるスローガンではありません。経営者が旗を掲げ、判断基準を明確にし、両部門が共通の地図を持って動くことです。そうして初めて、顧客との約束を守りつつ新たな案件に挑戦できます。
駆動力を生み出す「販売」と、車体をコントロールする「製造」の連携、連動が、製造業の生き残りには欠かせないのです。経営者は、自分の想いを製販一体の場で伝えなければなりません。
●経営者の想いを、言葉、数字、形にする
経営者の仕事は社外にあります。そして、経営者が工場にいなくても、受注可否判断を経営者の望むように下せるように、右腕役や現場キーパーソンを指導しなければなりません。
経営者は自らの意志を「言葉」「数字」「形」にして示す必要があります。受注可否判断は意思決定のなかでも、重要度の高いものです。そうであるなら、それを形にします。
今回の「新規受注検討リスト」は、その象徴です。口頭で「挑戦しろ」と言っても人は動きません。数字に落とし込み、形にして初めて、社員はそれを共通のルールとして理解します。
地図のない航海から、羅針盤を手にした航海に変わるのです。経営者が工場を不在にしていても、右腕役や現場キーパーソンは、経営者の意志に沿った、挑戦的な判断ができます。
そして、その経営者が、改めて、製販一体メンバーへ明確に示したのは二つです。
・納期を守るには製販、相互の相互の補完が必要であること
・責任は経営者が取るから大いに挑戦してほしいこと
これらは以前から口頭で伝えていましたが、なぜか力になりませんでした。それが、リストという「形」になった瞬間、議論が始まり、チームの血肉となったのです。
工場経営の本質は、経営者の想いを他人の力を借りて実現することにあります。したがって、経営者は、想いや意志を明示しなければならないのです。
明示されなければ、他人の協力を得られません。言語化、数値化、具体化――この三つが揃って初めて、他人はその想いを支えることができるのです。
経営者の意志が空気のように曖昧であれば、人は迷い、足並みは乱れます。しかし、それが形になれば、従業員はベクトルを揃えて同じ方向に進むことができるのです。
「言葉、数字、形」によって意志を伝えることが、製販一体を動かす源泉になります。言語化、数値化、具体化は、経営者にとって欠かせないスキルです。実践で磨きます。
次は貴社が挑戦する番です!
成長する現場は、言語化、数値化、具体化された経営者の意志に沿って挑戦的に判断する
衰退する現場は、経営者の意志が口頭でしか示されないのでベクトルが揃わず守りに入る